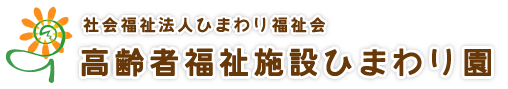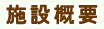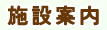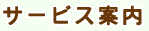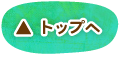熊本震災支援4
2016年04月27日
前回の支援活動報告の続きです。
坂本の里一灯苑は、ライフラインが比較的早期に復旧していたようですが、前々日に突如濁り水が発生し、ガス管の亀裂から厨房床下へガスが流入する等、一時大変な状況だったようです。
施設長様から地震発生時の状況を伺いましたが、発電機の整備や食料の備蓄等、もともと災害への備えに力を入れておられたため、混乱を最小限にとどめることができたように受け止めました。
しかしながら、少ない人員で入居者の方を支え続けた介護職員の皆さんは、心身ともにストレスの連続だったことが想像に難くありません。特に2度にわたる本震の発生や、復旧したライフラインが再び寸断された時の徒労感は、どれほどのものだったのでしょうか。
ひまわり園でも防災関係について何度も議論を重ねてきましたが、地域の高齢者を受け入れる福祉避難所の必要性やその運営の困難さ等、いろいろと考えさせられる機会になりました。
その後、福岡のいきいき八田に戻り、もう一つの被災施設「たくまの里」で活動した支援者等と合流し、互いに意見交換を行いました。たくまの里チームは、避難して来られた地域住民の方を対象にハヤシライスの炊き出しを行ったようです。
支援活動2日目

全国の21老福連会員施設から大量に送られた支援物資を車に積み込み、再び坂本の里一灯苑に届けました。
物流が格段によくなったので、これで初動の支援を終了する目途がつきました。余った分は一灯苑さんから地域住民の方へ配られる予定です。再び大きな余震があったとしても、これだけの水・食料・日用品・燃料があれば、当面しのげると思います。

この日は施設長様は不在でしたが、特養責任者の長尾様が出迎えてくださいました。

長尾様は、「子供が怖がるので」と前日まで車中で寝泊まりしておられたそうですが、私たちに常に笑顔で応対してくださったのが印象に残りました。苦しいときに笑顔で周囲を鼓舞する、リーダーのあるべき姿を見たように思います。私だったら笑えるだろうか、とても自信がありません。
その後、大阪チームは「たくまの里」で再び断水が発生したとの情報が入り、その足で支援に出発しました。私たち島根チームは予定の活動を終え、帰路に向かいます。

地震の凄まじさをまざまざと見せつけられる一方、数キロ離れたところでは進学塾に通う小学生の姿があったり、サッカーや野球の練習をする学生、ゲートボールに興じる高齢者の方々・・・「日常」と「非日常」が交互に視界に入り、頭の中で整理がつきません。
「建物の外観は問題なくても、中はめちゃくちゃなんですよ」と地元コンビニの店員さん。一見日常に見える風景の中に、どれほどの人の想いが込められているのでしょうか。
自分がなぜうしろめたい気持ちになったのか、その理由をぼんやり考えながら帰路につきました。

(中継地点のいきいき八田にて)
一緒に活動した長命園の須山園長、谷口副園長、本当にお疲れ様でした。また忘れ物を取りにお邪魔しますので、美味しいコーヒーご馳走してください。
21老福連のカンパの受け付けは28日に一旦終了します。ご協力ありがとうございました。